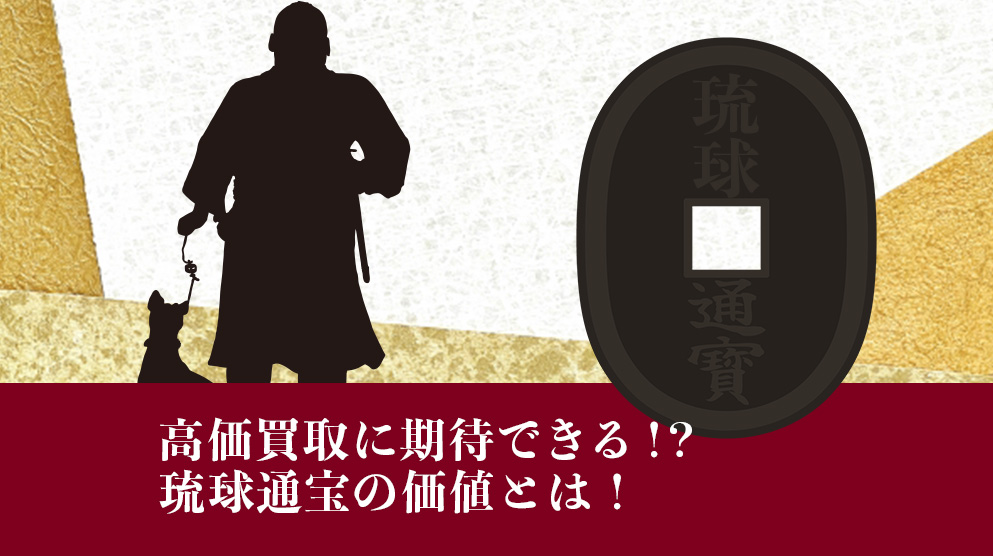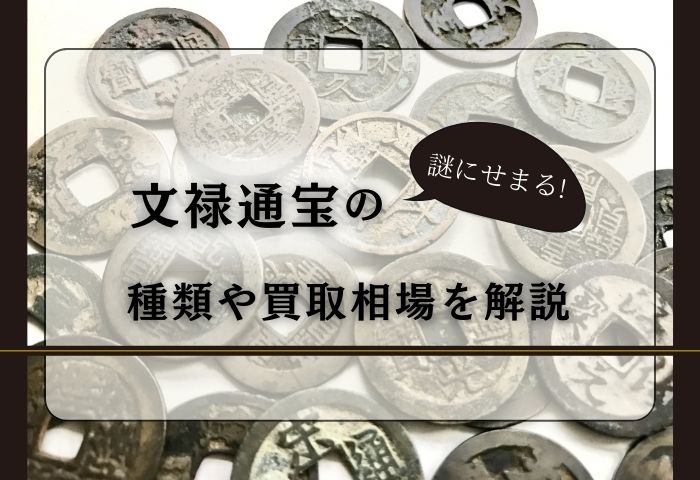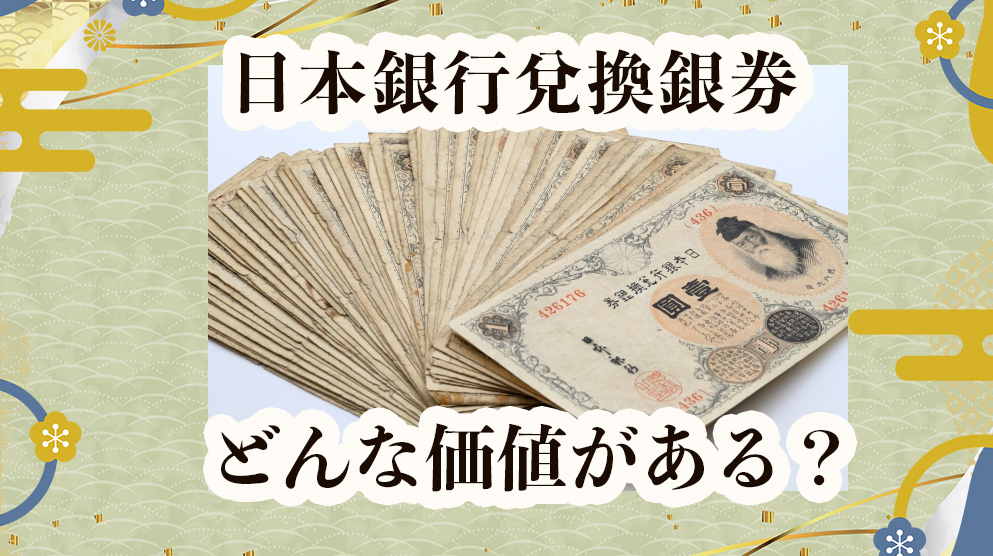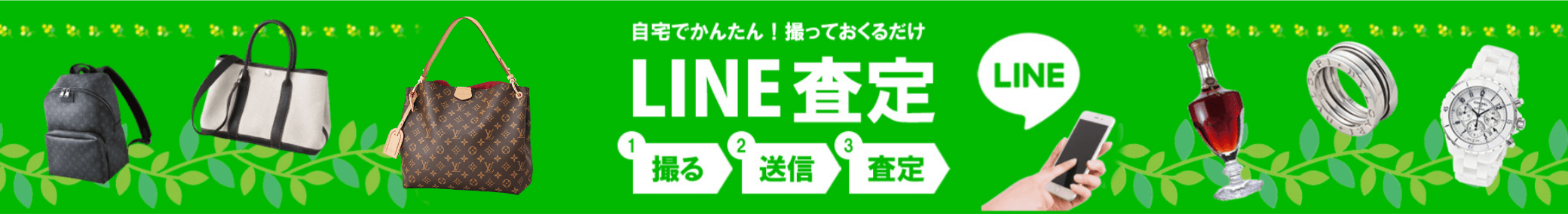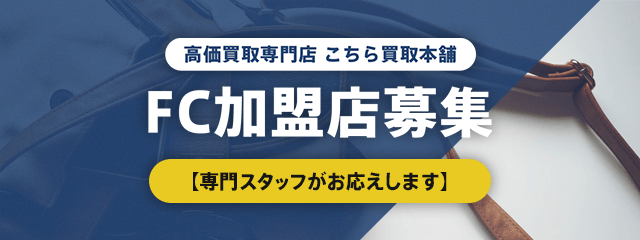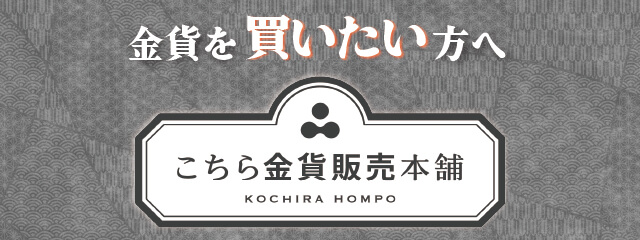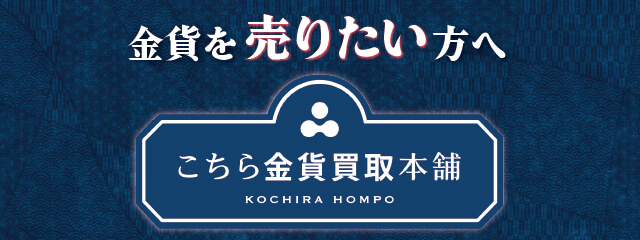旧紙幣・古紙幣の歴史や買取価格など、古いお札の価値にまつわる情報を一覧で解説!

古紙幣の歴史を解いていくと、古くは1600年代にまで遡ります。
それぞれの時代でデザインやサイズなども変化しており、コレクションして楽しむ人も少なくありません。ただ、古紙幣の価値は希少度などによって買取価格が異なります。
今回は、古紙幣に注目してどのようなものがあるのか、高価買取してもらうためのコツなどさまざまな情報を解説していきます。
旧紙幣・古紙幣とは?
古紙幣とは、旧紙幣よりさらに古いお札を指します。旧紙幣は、すでに発行停止になっているお札のことで、法令に基づく特別措置がとられていなければ使用可能です。一方、古紙幣はお金として使用することはできません。
そのため、コレクション要素が強い紙幣と言えます。ただ、歴史が古いお札であるほど紙質が良い状態とは言えないため、劣化しやすいのが難点です。つまり、丁寧に保存されていて傷みが少ないものは、それだけ価値が高くなります。
かつては、大判・小判といった貨幣が主流で使用されていましたが、その結果、原料となる金属が不足する事態となりました。そこで誕生したのが、原料費が安く持ち運びしやすい軽さの紙幣だったと言われています。
古紙幣のなかには、同じ種類であっても文字の書体違いやデザイン違いなどもあり、そういったものはより価値が高くなる傾向です。通常のデザインの紙幣と比較してレア度が高いということで、プレミア価格がついている古紙幣もあります。
とくに、発行した年代が古いもの、発行枚数が少ないものなどは手に入れることが困難となるため、プレミア価格となり通常紙幣の10倍で買取されるケースも珍しくありません。
古紙幣は、紙幣の認知度や理解が低かった時代もあったため、どのようなものが良いのかの評価が日々変化してきました。結果的に、紙幣が全国に浸透し、国民が安心して使用できるまで、さまざまな紙幣が誕生しました。
古紙幣の歴史
古紙幣の歴史は1600年、関ケ原の戦いの頃に伊勢(三重県辺り)の商人たちの間で作られた「山田羽書」が最初の紙幣だったと言われています。
その後、1661年頃からは各藩において貨幣の代わりとして利用できる「藩札」が製造されるようになりました。藩札は、貨幣の代わりだったこともあり、「金札」「銀札」「銭札」といった呼ばれ方をしていたと伝わっています。
ただ、この藩札は各藩でデザインもサイズも異なるものであり、紙幣の価値の信頼性に不信感を抱いた領民による一揆が起こる事態になってしまいました。
1868年、廃藩置県で江戸幕府から明治政府に変わり、藩札は使用禁止となっています。この際、明治政府が日本で初めて全国共通の「太政官札」を発行しました。
しかし、2年後の1870年頃には偽造紙幣が出回るようになったため、1872年、ドイツに依頼していた新紙幣「ゲルマン紙幣」を発行するようになりました。ゲルマン紙幣は、それまで日本になかった紙幣の偽造防止技術が取り入れられています。
その技術とは、主な模様を黒色で凹版印刷し、地紋を青色インクで凸版印刷するというものでした。さらに、1873年には、アメリカに依頼していた国立銀行紙幣(旧券)が発行されています。
1881年には、現状発行されている紙幣のように肖像画が取り入れられるようになりました。初めて取り入れられた肖像画は、神功皇后です。1885年、日本銀行兌換銀券が発行されました。
このときは、大黒天の肖像画が取り入れられており、人気のお札となったことは有名です。大日本帝国憲法が公布された1888年、歴史上の有名人物である菅原道真や藤原鎌足などの肖像画を取り入れた改造兌換銀券が1891年頃にかけて発行されています。
1891年に発行された改造100円券は過去最大のサイズで、縦13cm、横21cmもありました。そして、1899年、金本位制が導入されるようになり、「日本銀行兌換券」が発行されています。
通常の紙幣のほかには、戦争時に使用されていた特別なお札である軍票(軍用手票)もありました。戦争時は、日本以外の国で物資の調達をしたり給料の支払いをしたりする必要があります。
そこで、当時日本政府が発行した共通の紙幣が軍票でした。ただ、軍票は終戦後に多くのものが無価値となっています。軍票が使用されていたのは、ビルマやオセアニア地方、フィリピン、マレー、中国などです。
とくに、中国では7種類ほどの軍票を発行し、使用していました。
旧紙幣の歴史
明治以降に発行された日本の旧紙幣について詳しく説明していきます。
日本の紙幣の歴史は、明治時代から現代にかけて、さまざまな額面とデザインの変遷を経ています。旧紙幣とは明治時代以降に流通し、現在発行が停止された紙幣のことです。聖徳太子の壱万円札や五千円札、伊藤博文の千円札、板垣退助の百円札などが記憶にあると思います。
旧紙幣はいつまで使用できるのか?今も使えるのか?という疑問があると思いますが、現在でも使用可能な紙幣は数多く存在し、日本銀行が2019年までに発行した全53種類の紙幣のうち22種類が現在も使用可能です。
とはいえ、実際にお店で旧紙幣を使用するのは厳しいのが現状です。その場合、銀行などの金融機関で額面通りの金額で交換することができます。しかし、その現在も使用可能な旧紙幣のなかに額面を超える額の価値のある紙幣が存在します。
初期の紙幣(明治時代-大正時代初期)
明治時代に日本政府で初めて紙幣が発行され、その後もさまざまな額面が追加されました。このときの紙幣は非常にシンプルで、日本の歴史上重要な人物の肖像が印刷されていました。大正時代には紙幣のデザインを精査。美術的な要素が強調され、美しい風景や伝統的な文化が描かれるようになりました。
昭和(1926年-1989年)
昭和初期の1927年(昭和2年)。関東大震災後の経済混乱で銀行破綻の情報が流れたことにより、人々が預金の引き出しに殺到する騒ぎが起こりました。日本銀行は各銀行に融通する紙幣が必要になり、急遽紙幣の発行を決めました。
全国にある銀行の臨時休業中の2日間で新紙幣を製造することになりました。通常の印刷では間に合わないため、表面はオフセット印刷による彩紋の図柄のみ、裏面は印刷を省いた白紙の状態で製造しました。
結果、不眠不休の作業の末、紙幣不足危機は回避されたのです。昭和中期には高額面の3種類の紙幣が発行され、経済の安定と発展を支えました。一万円札、五千円札、千円札が存在し、日本文化や歴史に関連するデザインが多く取り入れられています。
1944年(昭和19年)から1945年(昭和20年)にかけて、戦時中の資金調達のために急いで増刷された「軍票」と呼ばれる特殊な紙幣も発行されました。昭和後期には、デザインがより近代的に変化しました。紙幣には日本の歴史上の人物や文化的な要素が反映され、セキュリティ対策も強化されました。
平成(1989年-2019年)
平成には従来のデザインに変更が加わり、新紙幣として2,000円札が発行されました。小野小町と紫式部が描かれており、10,000円札には福沢諭吉の肖像が使用されています。これらの紙幣は、日本の歴史や文化を反映し、美術的な要素を含んでおり、紙幣の発行技術の進化が見て取れます。
令和(2019年-現在)
2024年(令和6年7月)に偽造防止などを目的に、一万円札、五千円札、千円札の3種類のデザインが一新された紙幣が発行される予定です。一万円札は現行の福沢諭吉から渋沢栄一に、五千円札は樋口一葉から津田梅子に、千円札は野口英世から北里柴三郎にそれぞれ変わります。
新紙幣には、世界で初めてとなる最先端ホログラム技術が導入され、紙幣を斜めにすると肖像が立体的に見えます。「透かし」の部分は、肖像を映し出すのみではなく、紙の厚みを細微にし、精細度の高い模様を作り上げています。
また、視力の弱い人などにも判別しやすいよう数字のサイズを大きくし、触って紙幣の種類を識別できるよう、凹凸をつけるなどの工夫もされています。
冒頭でも説明しましたが、旧紙幣・古紙幣は額面よりも高い額で買い取ってもらえることがあります。旧紙幣のなかには現行紙幣も多く、そういった旧紙幣は額面での買い取りとなるのが基本です。紙幣にはアルファベットと数字が組み合わさった番号が印刷されています。
印刷されている紙幣番号が1番・ゾロ目・キリ番・階段などの場合、紙幣の価値は一気に高騰し、高額買取が期待できます。また、エラー紙幣(印刷ミス・印刷ズレ・耳付き・記号違い等)は額面の100倍以上の価値がつくことがあります。
「AA券」や「ZZ-Z券」はプレミアが付くことで有名です。AA券とは「A111111A」というようにAで始まりAで終わる番号の紙幣です。市場に出回ることはほぼないため、非常に価値の高い紙幣となります。ZZ-Z券とはAA券とは逆に「ZZ564987Z」というようにZで始まりZで終わる番号の紙幣です。最後に製造された紙幣がZZ-Z券です。ZZ-Z券はAA券ほど高値ではありませんが、額面以上の価値はあります。
旧紙幣・古紙幣一覧
明治通宝
「明治通宝」とは明治初期に日本政府により発行された国家紙幣のことで、日本では初めての西洋式印刷技術によって作られた歴史的紙幣としてその名が知れ渡っています。またドイツのフランクフルトにあるドンドルフ社とナウマン社で製造されたことから「ゲルマン札」という別名がありますが、「新紙幣」と呼ばれることもあります。
現在のお札のように横向きでなく縦向きにデザインされており、表面は左右対称の龍と鳳凰が対になって向き合い、中央に額面と明治通宝の文字があり、裏面には円形の多種多様なデザインが施され、大蔵卿印が赤インクで印刷されています。
明治通宝が発行される前は、「太政官札」「為替会社札」「民部省札」「府県札」などの紙幣が存在し、製造元がさまざまだったことから統制が取れず、偽造紙幣が横行しました。その背景から、政府は貨幣制度を一新、「円」を導入し、偽造されにくい近代的紙幣・明治通宝の発行を行いました。
明治通宝は日本全国で流通した初めての統一紙幣であり、現行紙幣の原型と言われ、発行された種類は全部で9種類、デザインは同じですが額面ごとに色分けされています。
100円券
明治通宝のなかでの最高額で、希少価値が高く、約24,000枚がドンドルフ社とナウマン社で印刷されたと言われており、現存数は10枚にも満たないので鑑定額も高額になります。価値が高すぎるため現在取引実績は確認されておらず、査定依頼をしても買取自体を断られることもあります。
50円券
50円券は100円券同様に発行枚数が23,000枚と一番少なく、希少価値が高い紙幣となります。やはりこちらも現時点で取引事例がないので希少性が高く、査定額もかなりの数字となるため、業者によっては対応できない場合があります。
10円券
10円券は日本とドイツで印刷され、約2,700,000枚発行されました。希少価値は高いですが、売買された事例が複数あります。保存状態によっては数十万円という査定が期待できますが、明治通宝は劣化しやすいため、そこまでの高額になるのは稀となります。
5円券
5円券はすべてドイツで印刷されたので劣化が激しく、保存状態が良いものが少ないため、原型を保ち美品であれば数十万円という高額査定が期待できます。
2円券
2円券は当時ドイツで印刷されましたが、その後日本でも印刷を行い、合わせて1,000万枚以上発行されており、現存数が明治通宝のなかでも一番多いと言われています。ほかの明治通宝と比較した場合、査定は低めですが、買取相場としては数万円になります。保存状態が良ければそれ以上になる可能性があります。
1円券
1円券は発行枚数の多い明治通宝と言われ、日本で大量に印刷されました。保存状態が良いものが多いため、明治通宝のなかでは比較的希少価値が低めとなっています。しかし、状態によって1万円前後の査定価格がつくことが多く、古紙幣のなかでは価値が高い部類になります。
半円券
半円券は額面としては1円の半分である50銭となり、「50銭券」と表されることもあります。発行枚数が少なく、印刷はドイツでされたものしかありません。現存している半円券は劣化が激しいものが多いため、1円券と比べると希少価値が高いと言われています。
買取査定は1万円以上となりますが、保存状態が悪いため、数千円の買取価格になりやすいです。
20銭券
20銭券はすべてドイツで発行され、明治通宝のなかでは2番目に発行枚数が多く、市場でもたくさん見かけます。希少性が高くはないですが、保存状態が良ければ1万円前後の買取査定になります。
10銭券
10銭券は明治通宝のなかで1番の発行枚数になります。ほかの明治通宝と比較した場合、価値は低く、買取査定は数百円から数千円になります。
1878年(明治11年)、貢納金のなかに明治通宝の贋札が発見されました。明治通宝はどの額面も同じデザインであったことから、偽物が大量に作られたため、古紙幣のなかでも偽物が多く、現在でも出回っており注意が必要です。
偽物は、裏面にある大蔵卿印の明治通宝の「通」という文字に違いがあります。本物の大蔵卿印は、細い線と太い線が使われていますが、偽物はほぼ同じ太さの線になっており、本物と比べると膨らんだような字体になっています。
明治通宝について詳しくはこちら↓
明治通宝の希少な100円券や5円券の価値は?その他の種類も一覧で解説!
旧国立銀行券
「旧国立銀行券」は、国立銀行が明治初期に発行した紙幣で、コンチネンタル・バンク・ノート社で発行されたので「アメリカ札」とも呼ばれています。旧国立銀行券には日本神話など歴史上の一場面が印刷されており、兌換文や公債証書引当文などが印字されているデザインになっています。
これらの文言は当時、アメリカ紙幣にも記載されていた内容を模倣して日本語訳したもので、当時のドル紙幣とデザインがよく似ています。1816年(文化13年)にイギリスで開始した、金を通貨の価値基準とする制度・金本位制が、国際的に流行っていました。
当時の日本は政府発行の明治通宝が流通していたのですが、金と交換できる紙幣ではなく「不換紙幣(ふかんしへい)」と呼ばれるものだったため、金本位制を取り入れることによって通貨の安定を図ろうと、民間の銀行が「兌換紙幣(だかんしへい)」を発行する制度として1872年(明治5年)に国立銀行条例を制定。
金と交換できる兌換紙幣として旧国立銀行券を発行しました。民間で国立銀行を設立し、兌換紙幣を発行させることで、政府は金本位制度の確立を民間に委ねたと言われています。
旧国立銀行券は額面ごとに異なるデザインで、5種類発行されました。しかし紙幣整理の政策によって1899年(明治32年)に通用禁止となり、回収され現存数が少ないと言われています。古紙幣のなかでは希少価値が高いので、保存状態が良ければ買取価格に期待大です。
20円札
旧国立銀行券のなかでは最高額面である20円札の表面は、スサノオミコトとヤマタノオロチが採用され、裏面は日本神話の一場面が印刷されています。非常に希少価値が高く、新品未使用の美品であれば数千万円の価値がつくとも言われています。一般的な査定としては数百万円になることが多く、普通の状態でも高額になる傾向があります。
10円札
20円札同様、10円札も希少価値がとても高く、プレミアがついているものとなります。買取査定は通常数十万~数百万円になりますが、新品未使用の場合は1,000万円以上の価格がつくこともあります。10円札の表面は、日本の古典音楽である雅楽を演奏する様子が描かれており、裏面は神功皇后が朝鮮を侵略した「神功皇后征韓」の伝説が描かれています。
5円札
5円札のデザインの表面は田植えと稲刈り、裏面には日本橋と富士山という日本固有の親しみやすいモチーフが描かれています。ほかの旧国立銀行券と比較した場合、買取査定が低めにはなりますが、数十万円の価値があります。未使用で保存状態の良いものとなれば、数百万円の査定額になることもあります。
2円札
2円札の買取相場は数万円~数十万円ほどで、未使用品の場合は数百万円になる可能性があります。旧国立銀行券の額面のなかでは価値が低めになりますが、古紙幣としては高値がつく種類になります。2円札のデザインは、表面に南北朝時代の武将・新田義貞と児島高徳、裏面は江戸城本丸の書院出二重櫓と御書院二重櫓が印刷されています。
1円札
1円札の表面には仁徳天皇時代の将軍・上毛野田道と、戦に使用された兵船が、裏面には鎌倉時代中期に起きたモンゴルの日本侵略を目的とした「元寇」という出来事が描かれています。
発行枚数が多く、旧国立銀行券のなかでは一番価値が低く、状態によって査定額は数万円となります。しかし、額面1円が数万円という価値になるので、古紙幣としては高い価値を持つ種類といえます。
旧国立銀行券について詳しくはこちら↓
旧国立銀行券の価値は?種類別に買取相場をご紹介!
新国立銀行券
国立銀行券には「旧国立銀行券」と「新国立銀行券」が存在します。この2つの銀行券の違いは、新旧の名前の差だけではありません。はっきりとした違いがあり、性質も意味合いも異なる紙幣なのです。
旧国立銀行券は、金と同等の価値が保証されており、金との交換ができる紙幣として発行された兌換紙幣になります。
新国立銀行券はというと、金との交換はできません。金と同等の価値も保証されていない不換紙幣となります。新国立銀行券は5円札と1円札の2種類の額面のみが発行されました。
当時、劣化と偽造が問題になっていた明治通宝に代わり、改造紙幣が発行される時期のため、紙幣の製造業者の負担が増えたことにより新国立銀行券は2種類しか発行できなかったとされています。
1円札
1円札のデザインは、表面は2人の水兵、裏面は胡坐をかいて微笑む恵比寿様が描かれています。表面の水兵は富国強兵の象徴でもあり、通称名として「水兵1円」とも呼ばれていました。
5円札
5円札のデザインは、表面には鉄を打って農具や刃物の製造や修理を行う鍛冶屋、裏面は1円札同様恵比寿様が描かれています。表面の鍛冶屋は、将来日本が農業から工業を軸に進むという意味が込められていたと言われ、「鍛冶屋5円」という愛称で呼ばれていました。
新国立銀行券は2種類とも価値が非常に高く、保存状態の良いものは10万円以上の値がつくことも多々あります。
旧国立銀行券は金本位制に則って発行されましたが、日本は金不足に陥ったことで兌換紙幣が発行できなくなり、1876年(明治9年)に経済状況の悪化を防ぐ目的で、不換紙幣である新国立銀行券を発行することになりました。
翌年1877年(明治9年)、西南戦争の戦費を賄うために、新国立銀行券が大量に発行されたのですが、激しいインフレーションを起こし、銀行制度を整備するために日本銀行を設立。同時に新国立銀行券・旧国立銀行券は回収され、国立銀行券は1899年(明治11年)12月に運用停止となりました。
新国立銀行券について詳しくはこちら↓
新国立銀行券は買取可能?2種類の違いと価値をご紹介!
改造紙幣
改造紙幣は、大日本帝国政府が発行した「大日本帝國政府紙幣」という名称で、偽造が多発し、劣化もしやすかった明治通宝と交換するため、1881年(明治14年)2月に発行され、1899年(明治32年)に廃止になりました。
改造紙幣は20銭券・50銭券・1円券・5円券・10円券の5種類の額面が発行され、紙幣のデザインはイタリア人に委託され、偽札防止のために最高の技術を駆使して制作されました。5円と10円券の表面の肖像は神功皇后が採用され、すべての改造紙幣に菊花の勲章が描かれていたため、「神功皇后札」「菊花章紙幣」とも呼ばれました。
神功皇后の肖像は文献資料を参考にしつつ、紙幣局の女性職員をモデルにしたことで西洋風な顔立ちになっています。1円券以上の表面及び50銭券以下の裏面には、記録局長の割印が印刷されています。5円券以上には偽造防止のために初めて透かしが導入され、以降発行された日本銀行券にも引き継がれており、今日の日本銀行券の様式の礎になった存在と言えます。
全体的に現存数が少なく、現在の買取相場は20銭券・50銭券は美品の場合数十万円になり、普通品で数千円~数万円ほど。1円券は状態にもよりますが、数千円~数万円、5円券・10円券は数万円~数十万円になります。
改造紙幣について詳しくはこちら↓
改造紙幣は売れるの?現在の買取価値や、歴史を種類別に解説!
日本銀行兌換銀券(旧兌換銀行券)
10年以降、明治政府が不換紙幣を大量発行した結果、日本は激しいインフレーションを起こしていました。混乱した紙幣発行政策を改善するため、1882年(明治15年)に日本銀行が設立され、明治18年には新しいお札の1円、5円、10円、100円、4種類が発行されました。
銀貨との交換が保証されたお札のため、「日本銀行兌換銀行券」とも呼ばれました。また、すべてに大黒天が印刷されていたことから「大黒札」とも呼ばれ、偽造防止対策として当時の写真では写りにくかった青インキで印刷されています。なお、1円券だけは現在でも額面が1円として使用可能です。
過去に発行されたお札は紙の強度が弱く、劣化が著しかったので、日本銀行兌換銀券は紙の強度を高めるためにコンニャク粉が混ぜられたのですが、虫やネズミに食べられてしまう被害が多発してしまいました。さらに、偽造防止のために特殊インクを使用しましたが、このインクが硫化水素に対して化学反応を起こすことが判明。
日本銀行兌換銀券を温泉へ持っていくと変色してしまい、偽造券なのではないか?と騒動になったという一幕も。このように、紙幣の強化・偽造防止に努めたつもりの製造方法が、裏目に出る結果になってしまった日本銀行兌換銀券は欠陥紙幣となりました。
100円券
100円券は日本銀行兌換銀券では発行数が一番少ないので、希少価値が高く、現存数としては数枚しかないと言われている紙幣です。保存状態により、取引相場は数千万円の価値がつく可能性があります。
10円券
日本銀行兌換銀行券のなかで10円券が最初に発行されました。買取相場としては数十万円になりますが、保存状態が良いものは数百万円になることもあります。古紙幣のなかでとても価値が高いので、コレクターにも人気があります。
5円券
5円券の買取相場は10円券と同じ数十万円が一般的です。もし、未使用で美品の場合、数百万円の査定も期待大です。
1円券
1円券は現在でも1円として使用できる日本銀行兌換銀券になります。銀行の場合は額面通りになりますが、査定に出した場合は数万円、状態が良いものは、数十万円の場合もあるので1円として使用する前に買取業者に査定をしてもらいましょう。
日本銀行兌換銀券(旧兌換銀行券)について詳しくはこちら↓
日本銀行兌換銀券(旧兌換銀行券)の1円券などの価値やその他の種類も解説!
改造兌換銀行券
日本銀行兌換銀券の偽造防止や強化のために工夫をしたことが裏目に出てしまった理由から、100円券・10円券・5円券・1円券、4種類の「改造兌換銀行券」が発行されました。それぞれ違う人物の肖像画が描かれており、どれも希少価値が高く評価されています。
改造100円券
改造兌換銀行券の100円券には、大化の改新で有名な中心人物・藤原鎌足が描かれています。紙幣のデザインが眼鏡のような楕円形になっていることで、「メガネ100円」や「メガネ鎌足」という愛称がついています。現存数は100枚以下で、とても希少価値が高く、取引事例の報告はありません。本物の場合、数千万円の査定額がつくと言われています。
改造10円券
10円券の表面には、奈良時代から平安時代の転換期に近畿地方の河川の治水を行い、土木工事を数多くこなした貴族・和気清麻呂が肖像画に選ばれています。また、枠を囲むように8頭のイノシシがデザインされているため、「表猪10円札」と呼ばれることもあります。買取相場は数十万円ですが、新品未使用の美品の場合は100万円を超える査定の可能性も大いにあります。
改造5円券
5円券に選ばれたのは、学問の神様として現在も多くの人々に参拝されている菅原道真です。表面中央に配されている模様が、江戸時代に使用されていた量目測定の分銅だった後藤分銅に似ていることから、「分銅5円」とも呼ばれています。5円券は現存数が少なく、買取相場は普通品で10万円前後、状態の良い美品の場合は数百万円の値がつくこともあります。
改造1円券
1円券に採用されたのは、大和朝廷初期に活躍したという伝説上の人物、武内宿禰です。記述によれば第8代天皇の曽孫で、5朝に仕え、大臣となり、神功皇后を助けての新羅出兵などの功績があった人物。記番号が漢数字で表示されているため、「漢数字1円札」という名で呼ばれることも。買取相場は数千円で、未使用品の場合、数万円まで査定額がUPすることがあります。そして、現在も額面1円として使用できる紙幣でもあります。
甲号・乙号兌換銀行券
金と同じ価値が保証され、金と交換できる紙幣として、さまざまな日本銀行兌換券が発行されましたが、甲号・乙号兌換銀行券もそのひとつです。甲号・乙号兌換銀行券が発行されたのは、1899年(明治32年)。金が不足していた日本は、日清戦争に勝利したことで経済が潤い、念願だった金本位制度を採用。
そのときに発行されたのが甲号兌換銀行券です。乙号兌換銀行券が発行された経緯は、甲号兌換銀行券が偽造されはじめ、なんとか偽造できない精巧な紙幣をという目的で、1910年(明治43年)に発行されました。写真の技術が飛躍していた当時、日本ではその技術を使った紙幣の偽造が多発したと言われています。
そのため、透かしや写真の技術で偽造しにくかった緑色のインクを使用しました。約40年流通していた甲号兌換銀行券の特徴は、前期・後期に若干デザインが異なることです。肖像画に変化はありませんが、組番号に違いがあります。
前期に発行されたものは、万葉仮名で、後期に発行されたものは、アラビア数字でそれぞれ印刷されています。乙号兌換銀行券の特徴は、偽造防止としての最新技術が取り入れられていること。現在の紙幣と同じく透かし部分を丸く囲んでいるのは、乙号兌換銀行券が初めてと言われています。肖像画は当時の最先端だった彫刻技法を採用し、とても複雑なデザインになっています。
甲号兌換銀行券は100円・10円・5円の3種類、乙号兌換銀行券は5円の1種類が作られました。
甲号兌換銀行100円
甲号兌換銀行券の100円の表面、向かって右側には飛鳥時代の貴族・藤原鎌足、左側には奈良県にある藤原鎌足が祀られている談山神社が描かれています。裏面には1896年(明治29年)に竣工された東京都中央区にある、日本銀行券本店本館の全景が紫カラーで印刷されており、通称「裏紫100円」と呼ばれています。
買取相場は組番号によって変わってきます。前期の万葉仮名の場合は数十万円となり、後期のアラビア数字の場合だと数万円ほどになります。前期の万葉仮名は希少価値が高いので、未使用品は100万円を超えることもあります。
甲号兌換銀行10円
甲号兌換銀行券の10円は、表面には平安京建設の現場監督だった和気清麻呂と、京都御所の西側に鎮座し、和気清麻呂を祀る護王神社がデザインされているのが特徴です。裏面はイノシシが中央に配置され、その両脇に英語表記の額面が印字されていることから、「裏猪10円」という異名がつけられました。買取相場は前期、後期ともに数万円ほどになりますが、後期の未使用品の場合は数十万円の査定が期待できます。
甲号兌換銀行5円
甲号兌換銀行券の5円の表面中央には、古事記や日本書紀に登場する伝承上の人物・武内宿禰、その背景には武内宿禰が御祭神である宇倍神社が採用されています。中央に肖像画のある珍しい紙幣として「中央武内5円」と呼ばれています。前期は1万円前後が相場となりますが、未使用で美品の場合は数万円~10万円前後になることもあり、後期の方が価値が高いため、普通品でも高値が期待できます。
乙号兌換銀行5円
乙兌換銀行券の5円表面右側には、緑のインクで印刷された菅原道真と左側には透かしの大黒天が入っています。このお札は「透かし大黒5円」と呼ばれていますが、インクの見え方のせいで菅原道真の顔色が悪い印象を受けたため、別名「幽霊札」と呼ばれることもあります。買取相場は数千円~数万円となりますが、未使用で美品の場合は10万円前後の査定がつくことも。
甲号・乙号兌換銀行券について詳しくはこちら↓
甲号兌換銀行券と乙号兌換銀行券の価値を種類別に解説!
大正兌換銀行券
大正時代に発行された兌換銀行券の一種である大正兌換銀行券は20円券、10円券、5円券、1円券の4種類が発行されています。このお札が発行された経緯ですが、第一次世界大戦の真っ最中だった大正時代は日本製の武器の需要が高まり、日本の景気はとても良い状態でした。
そのため、紙幣がたくさん必要だったことから大正兌換銀行券という新たな紙幣が発行されました。当時、写真技術がかなり向上していたため、紙幣の偽造がされやすくなっていました。大正兌換銀行券は当時の流行に乗ったデザインに一新され、偽造防止対策に力を入れて発行されたと言われています。
大正兌換銀行券と名がついていますが、金との交換はできない紙幣です。第一次世界大戦が原因により、世界的に金本位制を停止していたため、日本も一時的に停止する体制をとっていました。
再び金本位制が復活した時のために、兌換紙幣の発行を続けていましたが、世界恐慌や昭和恐慌などで実現できなかったとされています。そして、時代は紙幣の発行額を国が管理する管理通貨制度になり、金本位制は完全廃止となりました。
20円札
20円券は大正兌換銀行券のなかでは一番希少価値が高いので、未使用品かつ美品の場合は50万円前後になるでしょう。20円札は菅原道真が採用され、横書き印字の額面から「横書き20円」と呼ばれています。大正兌換銀行券の20円札ですが、日本銀行が発行した紙幣で初の2のつく紙幣となります。買取相場は数万円ほどですが、未使用品で状態が良いものであれば数十万円の価値があります。
10円札
10円札の表面には珍しく左側に和気清麻呂、右側に護王神社がデザインされています。その見た目から「左和気10円札」との名前がつきました。多くの紙幣を発行した日本ですが、左側に肖像画を配した紙幣はこの紙幣のみです。貴重な古紙幣として注目されていますが、数千円~数万円が平均的な査定額になります。
5円札
「大正武内5円」「白ひげ5円」という異名を持つ5円札は、武内宿禰と宇倍神社が描かれています。 偽造防止目的で特殊な緑インクを使用していた乙号兌換銀行券5円札の菅原道真が、幽霊のように見えると不評だったことから、今回大正兌換銀行券5円札が発行されたと言われています。買取価格は数千円になることが多いですが、状態が良い場合は数万円にもなります。
1円札
1円券は現在も1円として使用可能ですが、どの種類も額面以上の査定額がつく可能性があります。デザインは異なりますが、5円札と同じく1円札にも武内宿禰の肖像画が採用され、記番号がアラビア数字で印刷されてることから「アラビア数字1円」と呼ばれています。買取相場は額面を大きく超える数十円~数百円になるので査定に出すことをおススメします。美品の場合は数千円になる可能性大です。
旧紙幣・古紙幣を高価買取してもらうには?
旧紙幣・古紙幣の多くは強度が低いため、今以上に劣化を防ぎ、現状維持に努めることが大事です。良い状態にしようと素人が手を加えるのは逆効果になります。昔の紙幣は劣化しやすい素材のため、細心の注意が必要です。綺麗にするのではなく、なるべくそのままの状態を保ちましょう。
そのためには紙幣専用アルバムなどに入れ、今以上に劣化しないように保管します。旧紙幣・古紙幣は破損しやすいので、保管方法はとても大切です。移動の際も紙幣専用アルバムや保管ケースごと持ち運ぶようにして、直に紙幣に触れることのないようにしましょう。
そして偽造紙幣もたくさん出回っていることから、フリマアプリなどで売却するとトラブルの元になることもあります。プロの鑑定士に査定してもらい、専門の買取業者に買い取ってもらうことです。古紙幣の価値がわからない業者に査定依頼をした場合、適正価格ではない評価になったり、安値で買い取られてしまい損をしてしまうことになります。
プレミアがつく旧紙幣・古紙幣
旧紙幣・古紙幣のなかにはプレミアがつくものが存在します。まずは紙幣番号をチェックしてください。例えば、「紙幣番号がゾロ目」「12345と数字が階段状になっている連番」などの古紙幣は、希少性が高いため、高価買取されています。
ほかにも、いわゆるキリ番、1000000のように2番目以降の数字が0でそろっているお札も希少性が高く高価買取の対象です。また、紙幣番号の000001番は「1番数字」と呼ばれており、通常では手に入れることができません。
なぜなら、1番数字のお札は最初に発行されたものであり、貨幣博物館が所有しているからです。もし、1番数字のお札を手に入れることができたとしたら、何らかの事情があって世に出回ったものとなるため、希少度はかなり高いと言えます。
また帯付きの紙幣は新札のため、未使用で状態が良いお札であると共に連番やゾロ目、キリ番が複数含まれる可能性もあるので高値になりやすいポイントと言えます。
耳付き紙幣もレア度が高く、高価買取されているものです。お札は、発行した際に規定サイズにカットしなければなりません。しかし、耳付き紙幣は、カット段階で部分的に紙が残っている状態です。
大量に紙幣を発行するため、そういったエラー紙幣も出ると感じる人もいるかもしれませんが、実際には多くありません。仮に、紙幣のカット段階で耳付き紙幣があったとしても、担当者がそれを確認した際に耳部分をカットするなど、何らかの対処をしています。つまり、耳付き紙幣が世に出回っていること自体がほとんどありません。
旧紙幣・古紙幣の現在の価値は?
古紙幣の現在の価値が気になる人も多いのではないでしょうか。いずれも状態により買取価格は変動しますが、古紙幣のなかには、買取価格が数百万円になるものもあります。自宅に価値が高い古紙幣がある場合は、まず見積もりを出してもらうのがおすすめです。
具体的には、旧国立銀行券の10円、20円はとくに価値があるとされており、状態が良いものであれば500万~600万円ほどの買取価格が提示されています。
また、日本銀行兌換券の200円(裏側が白いもの)も400万円前後で買取価格が提示されており、高価買取対象です。
旧兌換銀行券10円(大黒10円札)や甲号兌換銀行券100円(万葉記号)などは前述した古紙幣よりは安くなるものの、100万~150万円ほどの価値があるとされています。ただ、同じ旧兌換銀行券であっても、5円(裏大黒5円)は45万円ほど、1円(大黒1円札)は4万円ほどです。
甲号兌換銀行券も、同じ100円であってもアラビア記号札は45万円程度での買取となっています。額面が同じだったとしても、デザインによってその価値は半分以下に下がってしまう可能性もあることがわかるのではないでしょうか。
また、同銀行券の5円前期のものは7万円、5円後期は12万円ほどが相場となっています。10円前期は12万円、10円後期は15万円です。
明治時代にドイツに依頼して発行したゲルマン紙幣(明治通宝)は、金額によって価値が異なります。ゲルマン紙幣の20銭は8,000円前後ですが、10円は15万円ほど、5円は25万円ほどの買取価格です。
10銭、1円、2円については数万円程度で買取されています。江戸時代に登場した藩札は、歴史的な面でいえば高い価値がありますが、買取価格面で見ると2万~5万円前後です。
なかでも買取価格が高いのは、デザイン性に価値があると判断されている和歌山藩札で相場は5万円ほどとなっています。次に相場が高いのが峰山藩札で4万円ほどです。こちらは、峰山藩が小規模の藩であり、発行枚数自体も少ない点が買取価格に影響しています。
軍票で高価買取されているのは、1918~1920年まで出兵していたシベリアでの軍票である金5円や金10円です。こちらは、紙幣の状態にもよりますが約30万~40万円で買取されています。
次に、日露戦争時の軍票銀10円の買取相場は28万円前後です。中国の青島に出兵した際の軍票は銀紙幣ですが、銀10銭や20銭は約6万~7万円、銀1円は15万円前後、銀50銭は10万円ほどでの買取がされています。
旧紙幣・古紙幣を高額買取してもらうには保存状態が重要
古紙幣といっても種類が豊富にあり、買取の金額差が大きなものでは、10倍もの差がついているものもあるほどです。高価買取してもらうには、保存状態が良好であることが重要といえます。
古紙幣の紙質は、丈夫ではないため、触れたり日光や照明にあたったりすることで傷んでしまうケースも少なくありません。古紙幣を見つけたときには、丁寧に扱い、できれば早めに専門家に価値を見てもらうのがおすすめです。
この記事は参考になりましたか?