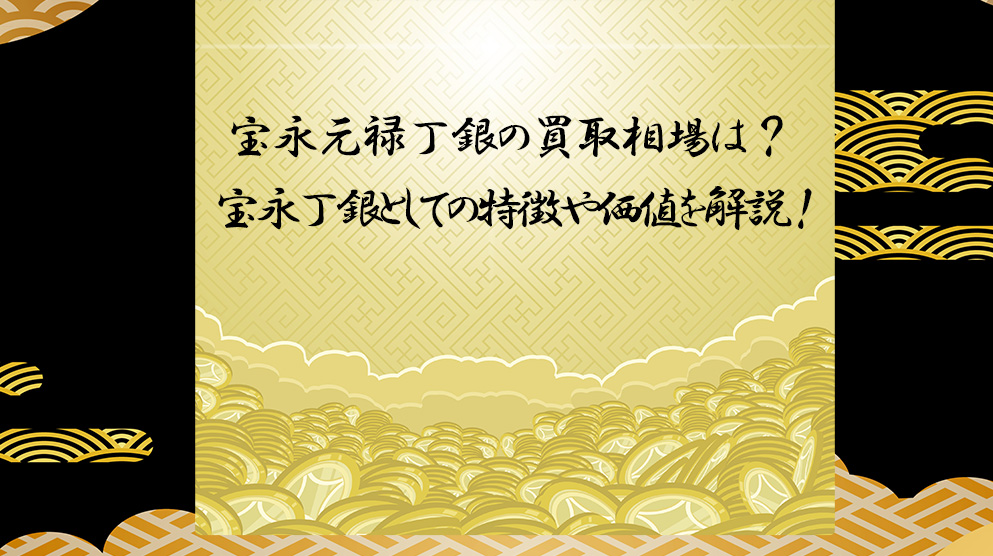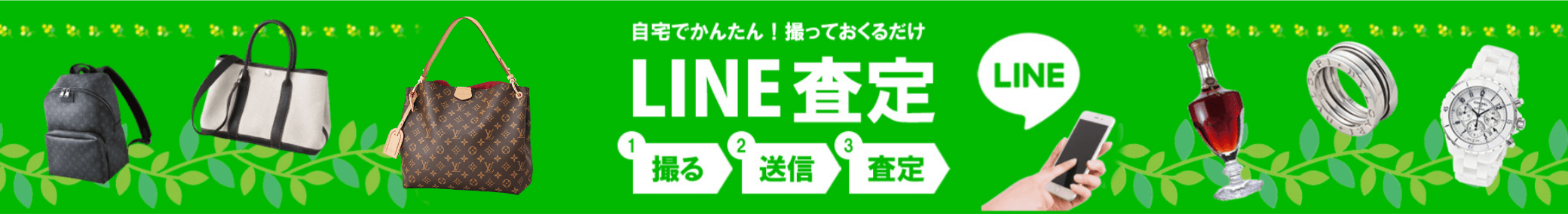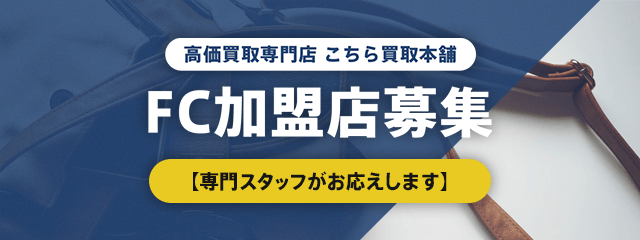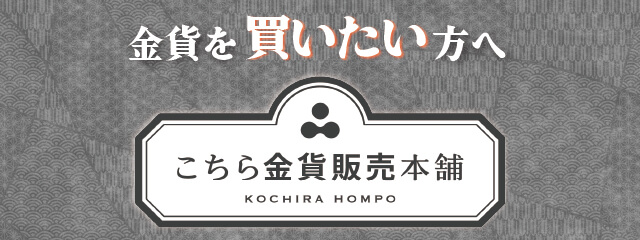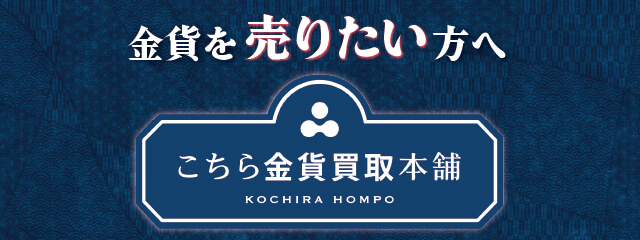近代金貨や銀貨を解説!明治~昭和に流通した近代貨幣の種類一覧や価値は?

古来より人々の生活に欠かせない貨幣ですが、なかでも明治から昭和の初めにかけて発行された「近代貨幣」は、現在も多くの人を魅了する硬貨のひとつです。
しかし、近代貨幣はどのような歴史を辿り、なぜ高い価値があるのでしょうか。この記事では、近代貨幣の歴史・価値・種類について、コレクションする際のメンテナンス方法も含めて解説します。
近代貨幣とは?
近代貨幣とは、明治時代から昭和の初めまでの期間に発行された貨幣を表します。近代銭と称されることもあり、大まかな種類としては金貨・銀貨・銅貨などがあります。
全国での流通を前提として設計されていたこれらの貨幣は、日本の経済の近代化と発展の過程で大きな役割を果たしました。現在利用されている貨幣と近代貨幣の大きな違いは、発行背景と設計思想です。
明治政府は西洋の近代国家をモデルとして、経済・貨幣制度の近代化を進めました。その結果、それまで日本で利用されていた貨幣とは違い、十進法を採用し、円・銭・厘という新たな単位を導入したのです。また、金本位制を採用することで、金貨を貨幣の基盤としました。
その後、昭和28年に制定された「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」が制定されると、1円未満の少額通貨は通貨としての効力を失いました。これにより、近代貨幣にあたる多くの硬貨が流通しなくなったのです。
しかし、近代貨幣の独特なデザインや材質などは今なお人気を博しており、日本の経済や文化の一部として、その価値を持ち続けています。
近代貨幣の歴史
近代貨幣はどのように作られ、どのような変遷を辿っていったのでしょうか。ここでは、近代貨幣の歴史について解説します。
近代貨幣の起源は、19世紀半ば、幕末の日本までさかのぼります。この時期、日本はアメリカや欧州諸国との間に不平等条約を結んだため、「洋銀」と呼ばれる外国の銀貨などの貨幣が多く日本に流入しました。
しかし、日本の金貨は海外の価値と比較して割安であったため、外国人が大量に日本の貨幣を入手し、海外へ流出させてしまったのです。
この問題に対応するため、幕府は「万延の改鋳」を行い、金銀の比価を国際水準に近づけることで、金貨の流出を抑えることに成功しました。
このような、西洋の貨幣制度を取り入れる状況のもと、明治維新がはじまると、明治政府は日本の貨幣制度をより近代化・西洋化することを目指しました。明治4年には新貨条例が制定され、従来の「両・分・朱」という貨幣単位を「円・銭・厘」に変更するなど、大きな変化が起こっています。
また、明治政府は国立銀行条例も制定し、国立銀行紙幣の発行を開始しました。しかし、西南戦争の戦費調達などで不換紙幣が大量に発行されて紙幣の価値が大きく下落するといった問題も抱えていました。
こうした背景のなか、明治15年には日本銀行が誕生しました。日本銀行は紙幣価値の安定を目指し、最初の日本銀行券である「大黒札」を発行。これが近代通貨の始まりと言えるでしょう。
さらに、19世紀末には、日本も先進国の動きに追随して「金本位制」を確立しています。これは通貨を金と交換可能なものとする制度で、これにより実際に額面と同価値の純金を含む「本位金貨」も発行されるようになりました。
しかし、1920年代に入ると、第一次世界大戦後の不況や関東大震災などさまざまな問題に直面し、昭和2年には金融恐慌が発生しました。各国は金本位制を継続することが難しくなり、金輸出の禁止や管理通貨制度への移行などが行われています。
日本でも大量の日本銀行券を発行し、モラトリアムを発令するなど、経済の安定を図りました。これにより、金貨・銀貨など近代貨幣はだんだんと姿を消していったのです。
近代金貨の種類や価値一覧
近代金貨は1870年(明治3年)から30年まで発行された「旧金貨」が5種類、1897年(明治30年)以降から昭和7年までに発行された「新金貨」が3種類の全8種類あり、それぞれ鋳造期間や発行枚数が異なるので残存数や価値にも差があります。
近代金貨は金の純度が高く、貴重な金貨として現在も高い相場で取引が行われています。製造された年や状態により査定額が変わってきますが、10万円以上になることがほとんどです。稀に1,000万円超えの値が付いた金貨も存在します。価格差が非常に大きい金貨となります。
取引の際は、額面や製造された年、金貨の価値や相場を知ることが大事になります。
ではこれから近代金貨を詳しく紹介していきます。
旧20円金貨(旧二十圓)
- 直径:3.506cm
- 重さ:33.33g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1870年(明治3年)
旧20円金貨は1870年(明治3年)から1892年(明治25年)に発行されました。かなり大型で、金の純度も高いことから「近代金貨の王様」と呼ばれています。
表面中央に大きな龍が描かれており、その龍を囲うように「大日本」「二十圓」「製造年」の文字が刻まれています。裏面には「桐紋」「菊紋」「桐枝」「日章」「八稜鏡」「日月旗」が配置されています。
初年度の発行枚数は46,139枚になりますが、それ以降の発行枚数が極端に少なかったため、近代金貨では極めて貴重な金貨となっています。
【並品の場合の相場】
- 明治3年発行:160万円~
- 明治9年発行:350万円~
- 明治10年発行:450万円~
- 明治13年発行:400万円~
旧10円金貨(旧十圓)
- 直径:2.942cm
- 重さ:16.66g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1871年(明治4年)
旧10円金貨は1871年(明治4年)から1880年(明治13年)に発行されました。この金貨は作られた年代に限らず、発行枚数が少ないため、買取価格も高くなります。旧20円金貨と似たデザインで、表面中央に「龍」、その周りに「大日本」「十圓」「製造年」の文字が刻まれています。
裏面には「桐と菊の紋」「日章」「菊と桐の枝」「八稜鏡」「日月旗」が配置されています。明治4年に鋳造開始されたときの発行枚数が多めなので、未使品の相場は65万円になります。明治9年以降の美品であれば450万円の価値になります。
【並品の場合の相場】
- 明治3年発行:22万円~
- 明治9年発行:350万円~
- 明治10年発行:400万円~
- 明治13年発行:400万円~
旧5円金貨(旧五圓) ※発行された年代によって縮小版が存在します
- 直径:2.384cm(縮小:2.182cm)
- 重さ:8.33g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1870年(明治3年)
旧5円金貨は1870年(明治3年)から1897年(明治30年)に発行されました。明治5年以降に発行されたものからサイズが小さくなったことで「縮小」と呼ばれています。デザインですが、採用されているモチーフに関しては表面も裏面も旧10円金貨と額面以外はとてもよく似ています。
発行枚数が多く、買取価格は近代金貨のなかでは比較的安めになります。
明治3年発行の旧5円金貨だけに「明瞭ウロコ」と名がついた、表面に刻まれた龍のウロコがはっきりした形のものが存在します。さらに明治5年以降に発行された縮小版の「明」の字で価値が変わります。
注目する場所は明の字の日部分四画目です。これが右側の月に触れている場合は「ハネ明」、離れている場合「トメ明」と呼ばれ、「ハネ明」は発行された年号次第で査定額が上がります。
【並品の場合の相場】
- 明治3年発行:7万5千円~
- 明治3年発行(明瞭ウロコ):9万円~
- 明治4年発行:7万円~
- 明治5~6年発行:5万円~
- 明治7~8年発行:9万円~
- 明治10~30年発行:37万円~
旧2円金貨(旧二圓) ※発行された年代によって縮小版が存在します
- 直径:1.748cm(縮小:1.697cm)
- 重さ:3.33g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1870年(明治3年)
旧2円金貨は1870年(明治3年)から1880年(明治13年)に発行されました。明治9年以降に作られたものから縮小版になっています。表面中央に「龍」、その周囲に「大日本」「ニ圓」「製造年」の文字が刻まれ、裏面は「菊・桐の紋と枝」「日章」「日月旗」「八稜鏡」が配置されています。明治7年・9年・10年・13年はそれぞれ39枚、178枚、87枚と全体的にみて発行数が少なくプレミアがついており、とても高い価値で取引されています。
【並品の場合の相場】
- 明治3年発行:4万円~
- 明治9年発行:250万円~
- 明治10年発行:300万円~
- 明治13年発行:300万円~
旧1円金貨(旧一圓) ※発行された年代によって縮小版が存在します
- 直径:1.351cm(縮小:1.212cm)
- 重さ:1.67g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1871年(明治4年)
旧1円金貨は1871年(明治4年)から1880年(明治13年)に発行されました。明治7年以降発行されたものは縮小版になります。表面中央のデザインは額面の「一圓」の文字と周囲には「大日本」、「製造年」が記されています。
旧1円金貨はサイズが小さく龍を刻めなかったため、ほかの金貨と違うデザインになりました。ですが、裏面は旧2円金貨と同じモチーフが配置されています。明治4年分のみ前期・後期に分けられ発行されています。
見分け方としては、まず表面の「明」の字の「日」と「月」の間の線が伸びているものがあり、それを「跳明」と呼ぶのですが、これは後期にだけある特徴です。前期と中期には線が飛び出ない「止明」と呼ばれるものになっています。
次に、「一」の字の左端の先端と「本」の字二画目の先端の向きが一致しているか、ずれているかに注目してください。向きが一致している場合は中期、ずれている場合は前期と後期になります。
【並品の場合の相場】
- 明治4年(前期)発行:3万円~
- 明治4年(後期)発行:1万5千円~
- 明治7年発行:12万5千円~
- 明治9年発行:45万円~
- 明治10年発行:125万円~
- 明治13年発行:175万円~
新20円金貨(新二十圓)
- 直径:2.878cm
- 重さ:16.67g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1897年(明治30年)
新20円金貨は1897年(明治30年)から1932年(昭和7年)に発行されました。総発行枚数約5,080万枚と言われ、近代金貨のなかでとても多い数になります。表面中央に「二十圓」の文字があり、周りを囲むモチーフはほかの新金貨と同じデザインになります。
裏面は「桐紋」「日章」「八稜鏡」が刻まれ、周りに「大日本」「二十圓」「製造年」の文字が描かれています。サイズ的に大きい金貨なので、買取相場は10万円を超えますが、とくに高値がつく年代は昭和5年~昭和6年です。
【並品の場合の相場】
- 明治39年発行:8万5千円~
- 明治40年(後期)発行:15万円~
- 明治41年発行:20万円~
- 明治42年発行:22万5千円~
- 大正元年発行:11万円~
- 大正9年発行:10万円~
- 昭和5年発行:200万円~
- 昭和6年発行:200万円~
新10円金貨(新十圓)
- 直径:2.121cm
- 重さ:8.33g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1897年(明治30年)
新10円金貨は1897年(明治30年)から1910年(明治43年)に発行されました。総発行枚数約2,000万枚と非常に多いですが、製造された年によって枚数が異なる金貨になります。表面中央に「十圓」の文字が配置され、その周囲に「菊花紋章」「菊枝と桐枝」が刻まれています。
裏面は「桐紋」「日章」「八稜鏡」が配置され、それらを囲むように「大日本」「十圓」「製造年」の文字が記されています。発行数が少なかった製造年のものはプレミア価値がつき、とくに希少価値が高いのは明治43年発行の新10円金貨で、美品であれば180万円程で取引されています。ほかにも昭和37年・昭和40年も10万円以上の査定額で取引されています。
【並品の場合の相場】
- 明治37年発行:10万円~
- 明治40年発行:6万円~
- 明治43年発行:60万円~
新5円金貨(新五圓)
- 直径:1.696cm
- 重さ:4.17g
- 品位:金900/銅100
- 発行年:1897年(明治30年)
新5円金貨は1897年(明治30年)から1930年(昭和5年)に約130万枚発行されました。表面中央に額面である「五圓」の文字、「菊花紋章」「菊枝と桐枝」が刻まれています。裏面は「桐紋」「日章」「八稜鏡」が配置され、「大日本」「五圓」「製造年」の字が周囲に描かれています。
当時金貨は、主に外国との取引に使用され、国内ではほとんど流通していませんでした。昭和63年に貨幣発行の新しい法律が制定されるまで使われており、最後に作られたのは昭和5年になりますが、現在も高い価値のある貨幣として注目されています。
【並品の場合の相場】
- 明治36年発行:7万5千円~
- 明治44年発行:4万円~
- 大正2年発行:5万円~
- 大正13年発行:5万円~
- 昭和5年発行:200万円~
近代銀貨の有名な種類の価値一覧
1円銀貨(一圓銀貨)
1円銀貨は1870年(明治3年)に鋳造開始されたのですが、当初は貿易用として台湾や朝鮮で使われていました。1871年(明治4年)日本の貨幣単位が「円(圓)」になり、1878年(明治11年)から国内でも流通するようになりました。
1897年(明治30年)に日本では通用停止になりましたが、使用が盛んだった台湾・朝鮮では流通が停止できなかったため、1914年(大正3年)まで鋳造されていたと言われています。
表面中央に龍が描かれ、その周囲に額面・製造年・大日本の文字が施されています。別名「龍一圓銀貨」と呼ばれることも。1円銀貨には「旧1圓銀貨」と「新1圓銀貨」が存在します。旧1圓銀貨は、1870年(明治3年)の1年間だけ鋳造されたのですが、使用目的が貿易限定だったため、日本では流通しませんでした。
旧1円銀貨は表面中央に宝珠を握った龍が刻まれ、その周囲を「大日本」「明治三年」「一圓」の文字が配されています。裏面中央には旭日が描かれ、上には「十六弁八重表菊紋」、両側に「五七桐花紋」があしらわれ、下には菊と桐の枝飾りが刻まれています。
新1圓銀貨は「新一圓大型銀貨」「新一圓小型銀貨」と2つの種類が存在し、大型の方が小型よりサイズが数ミリ大きく、縁が厚いのが特徴になります。新一圓大型銀貨は1874年(明治7年)に貿易専用銀貨として発行され、1878年(明治11年)に国内での使用許可がおりました。
新一圓小型銀貨は1887年(明治20年)に発行開始され、国内・貿易の両方で使用されました。どちらもデザインはほぼ同じで、表面中央に龍が描かれ、周囲を「大日本」「製造年」「重さ」「額面」「品位」が、裏面には「一圓」「菊紋」が刻まれています。
新一圓大型銀貨の買取相場は1万円以上の値が期待できますが、新一圓小型銀貨は数千円になることが多くなります。
1円銀貨について詳しくはこちら↓
一円銀貨(一圓銀貨)の価値とは?新・旧の違いや、本物と偽物の見分け方を解説!
旭日竜大型50銭銀貨
- 重さ:約12.5g
- 品位:銀約80/銅約20
- 直径:約32.1mm
旭日竜大型50銭銀貨は、1870年(明治3年)と1871年(明治4年)に鋳造された銀貨です。
旭日竜大型50銭銀貨はほかの50銭銀貨のなかでも直径が大きいです。当時、日本の象徴と言われた竜を表面にデザインし、その周りを「製造年」「額面」「大日本」の文字で囲みました。
裏面中央に旭日を配し、その周囲に「菊紋」「桐紋」を施してあるのが特徴です。旭日竜大型50銭は、一圓銀貨の補助として発行されたという経緯があります。銀の含有率が90%超えだった一圓銀貨に対して80%と品位を落とし、銀の国外流出を防ぐため、低品質の50銭として鋳造されました。
製造年によって価値が変動する特徴があります。買取相場は2千円前後~で未使用品の場合は2万円~になります。旭日竜大型50銭銀貨は模造品やレプリカ品が数多く出回っているため要注意です。
旭日竜大型50銭銀貨について詳しくはこちら↓
旭日竜大型50銭銀貨とは?買取相場と偽物の判別方法をご紹介!
旭日竜小型50銭銀貨
- 重さ:約12.5g
- 品位:銀約80/銅約20
- 直径:約30.9mm
旭日竜小型50銭銀貨は1871年(明治4年)に発行された銀貨で、重さや品位、デザインが旭日竜大型50銭銀貨とほとんど同じですが、直径と竜のサイズが若干異なります。竜が大きい方が「大竜」で、竜が小さい方が「小竜」になります。
買取相場としては大竜の方が高く、3万円程です。希少性が高いため、未使用品の場合20万円以上の値がつくこともあります。一方、小竜は2千円程になります。
竜50銭銀貨
- 重さ:約13.5g
- 品位:銀約80/銅約20
- 直径:約30.9mm
竜50銭銀貨は1873年(明治6年)~1905年(明治38年)まで発行され、表面は旭日竜大型50銭銀貨とほとんど同じですが、額面表記は「50SEN」となっています。国際化が進んでいた当時を反映していることがわかります。
そして裏面中央には、「五十銭」と大きく彫られています。明治30年以降、表と裏が逆になっているのが竜50銭銀貨の特徴です。買取相場ですが、未使用品は5千円~100万円、並品は千円~50万円と希少価値が高いため、査定額の幅に大きな差が出る銀貨なので状態次第で高額買取も珍しくありません。
旭日50銭銀貨
- 重さ:約10.1g
- 品位:銀約80/銅約20
- 直径:約27.3mm
旭日50銭銀貨は竜50銭銀貨鋳造停止後の1906年(明治39年)に発行されました。金貨銀貨の代表格だった竜図が廃止され、表面は額面の五十銭や菊紋、裏面は旭日、そしてそれを囲む小桜や額面が描かれています。大正時代に突入した後も鋳造は続きましたが、第一次世界大戦の影響を受け製造停止になりました。
買取相場ですが、美品でも数百円になることがほとんどです。理由としては、発行枚数が多いことから旭日竜大型50銭銀貨と比べて価値が低い傾向にあります。
発行数が少なかった大正初期に鋳造されたものであったとしても、高い査定額は期待できないでしょう。しかし美品かつ未使用品であれば、数万円になる可能性があります。
小型50銭銀貨
- 重さ:約5.0g
- 品位:銀約72/銅約28
- 直径:約23.5mm
1921年(大正10年)以降、暴騰していた銀相場が落ち着きをみせ、50銭銀貨の鋳造が復活したことから小型50銭銀貨が発行されました。ほかの50銭銀貨と比較すると、銀の品位が72%と若干低くなっており、サイズも小さく、重さも大幅に軽くなっています。
表面は「菊」「桐」「鳳凰」「五十銭」の文字が刻まれ、裏面は旭日を中心として、「大日本」「年号」が配されており、ほかの50銭銀貨と異なったデザインになっています。
「鳳凰50銭銀貨」「小型鳳凰50銭銀貨」の別名も存在します。買取相場は、未使用品の高いもので1万円程になりますが、昭和13年以前の発行の場合は、だいたいが数百円程で取引されています。
小型50銭銀貨(鳳凰50銭銀貨)について詳しくはこちら↓
小型50銭銀貨(鳳凰50銭銀貨)とは?プレミアがつく年号と買取相場について解説!
そのほかの硬貨
金や銀に代わる貨幣材料として銅・アルミ・ニッケル・亜鉛・錫なども使われてきました。これらは金や銀に比べて大量生産が可能であるため、一般的な取引に使われてきた歴史があります。
例えば、銅7.5割・ニッケル2.5割を含有する「10銭白銅貨」「菊5銭白銅貨」「大型5銭白銅貨」です。
そのほか、銅9.8割・鉛0.1割・亜鉛0.1割を含む「2銭銅貨」、銅9.5割・錫0.5割・亜鉛0.1割の「稲1銭青銅貨」など、さまざまなデザインのものが発行されています。
近代通貨のメンテナンス方法
硬貨のメンテナンスは一見すると簡単そうにも思えますが、コレクターの間で価値があるものにおいては注意が必要です。硬貨はその素材と保存状態によって、メンテナンスの方法が変わってきます。ここでは、とくに近代通貨のメンテナンス方法について詳しく解説します。
まずは、正しい保管を行うことです。硬貨の素材によっては空気中の酸素や湿度、温度変化によって変質することがあります。例えば、銅貨は空気中の酸素と反応しやすく、表面が酸化して緑青色に変わることがあります。
そのため、コインアルバムやコインホルダーなどの専用のケースに入れて保管することで、酸化や汚れを防ぐことが可能です。また、保管の際にはできる限り素手で触らないよう注意しましょう。
素手で触ると皮脂が付着し、酸化によって状態が悪くなる可能性があります。保管する場所としては、直射日光や紫外線、湿気を避け、風通しの良い冷暗所で保管することが望ましいです。一般的には、湿度は50%以下、温度は常温で、これらが安定した場所が適しています。
また、定期的なメンテナンスも欠かさないようにしましょう。お手入れの方法としては、手袋を使用して硬貨に直接触らないよう気をつけて、やわらかい布で軽く拭くことが基本です。
力を入れすぎると削れたり、傷の原因になったりするため、極力優しく拭くことが大切になります。さらに洗浄や磨きをする場合は、より細心の注意が必要です。洗浄するには、まず温めた石鹸水で優しく洗うようにしましょう。ただし、この工程は非常にデリケートで、力を入れすぎると貨幣の細かなデザインなどを損なう可能性があります。
石鹸水で落ちない汚れについては専門的な洗浄液を使用する場合もありますが、その際はさらに傷などをつけないよう気をつけるようにしましょう。
また、磨きについても、一般的には専門の磨き材を使用します。過度な磨きは硬貨の価値を下げる可能性もあるため、表面を傷つけないよう、また当時の状態を保っていない過度な綺麗さにしないような注意が必要です。
このように、硬貨の適切な保管やメンテナンスは価値を保管するためにとても重要ですが、適切な知識と技術がないと価値を損なう可能性もあります。自分でメンテナンスを行う場合には十分な知識を身につけるか、場合によっては専門家に依頼することがおすすめです。
近代通貨の歴史や価値を知って魅力を再発見しよう
近代貨幣はそのデザインの美しさから、高値で取引されているものも多くあります。しかし、歴史や価値の理由を知ることで、さらなる魅力も発見できるでしょう。
また、近代通貨を持っている場合は保管やメンテナンス方法を学ぶことも重要です。正しく取り扱って、その価値を保つことのできるコレクターを目指してみてください。
この記事は参考になりましたか?